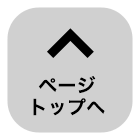「もっと節約しないといけないかも」、「もっと貯金を増やしたい」と思っていませんか。
同じ収入の人同士でも、上手に節約や貯金をしているかどうかで貯金額に差が出ているものですよね。今回は節約・貯金上手なワーママがしているコツを4つまとめてご紹介します。
節約・貯金上手なワーママがしているコツ4選
2020年3月3日

1.フルタイムからパートに変更し無駄を削減
心と体に余裕がなくて増える支出
貯金を増やすためには、働く時間を増やすことが効果的。最近では、ダブルワーク、トリプルワークというワードもよく聞かれます。
とはいえ、子どもが小さいうちは手がかかり、仕事と家庭の両立につらさを感じてしまうワーママがいるのも事実。仕事を終えてからの食事の用意に、惣菜やレトルト、冷凍食品に頼りがちな人もいるでしょう。
また、毎日の忙しさによるストレス解消のためと娯楽費や衣服費、外食費などが増えがちな家庭もあります。せっかく共稼ぎをしていても、支出が大きくて貯金が増えないというパターン、あるあるですよね。
自分に合う働く時間と貯金のペース
フルタイムで働き家事もしっかりこなす、そんなスーパーウーマンに皆がなれるわけではありません。人によって必要な睡眠時間も異なりますよね。子どもの年齢や実家に頼れるかなどの環境の違いも人それぞれです。
そのため、働き方をフルタイムからパートに切り替え、生活支出を減らすことに努めるワーママもいます。洗濯物の取り込みやお風呂洗いなどを手伝ってもらえるくらいに子どもが大きくなってから、働く時間を増やすという考え方もありますよね。
働き方を変えたいと思ったときは、どのくらい収入が減ることになるのか、食費や娯楽費、通信費などの家計見直しによる効果をどの程度得られそうか、冷静にシミュレーションしてみましょう。
2.通勤服は着回しで工夫
予算とアイテム数をざっくり管理
節約上手なワーママは、通勤服の着回しを工夫しています。オフィスに合う色使い、デザイン、清潔感、そして疲れにくいデザインといった基本のルールを決めて服選びをしましょう。トレンドを意識したファッションを楽しみたいときはプチプラも活用し、シーズン中に着倒してしまいましょう。
シンプルに「身の丈に合わない高価な服や枚数を買わない」「まだ着られるのに捨てるということのないようにする」の2点を意識するだけでも、衣服費をスリム化できます。
・1シーズンで新しく買うのは○着までと決める
・月、あるいは年単位で衣服費を決める
・カジュアルな通勤服は休日にも活用
・オフィスカジュアルなどの場合はおしゃれ着用洗剤が使えるアイテムを意識
・通勤服にヨレヨレ感が出たら休日用や日常着として活用
きれいに長く着るための工夫も
毎日洗濯するというわけにはいかないジャケットやコートなどのアウター。定番ものを長く活躍させるために、首回りや袖口の汚れに注意したいですよね。汚れ落としケアに時間がとれないワーママは、汚れが目立ちやすい白系のアイテムを避けましょう。
また、首回りの汚れ防止のためには、スカーフ、ストールなどが役立ちます。スカーフ好きな人は、ファッションのポイントにして楽しんでいますよね。
スカーフの目立ち方に抵抗を感じるワーママには、アウターの色に近い色のスカーフがおすすめです。バッグの持ち手にスカーフを結んでアクセサリー代わりにしておき、肌寒い仕事の帰り道にさっと首に巻く、いただきものを包んでバッグに入れておくなどの使い方にも活用できます。
3.食材まとめ買いは予算内で
忙しいワーママには、時間の効率的な使い方が大切。家族との和やかな時間をつくるためにも、無理のない自分なりの生活リズムをととのえたいものですよね。
食材をまとめ買いして買い物の時間を短縮するワーママが少なくありませんが、買いすぎて使い切れず、捨ててしまう食材が多くなるリスクが心配。食材を余らせてしまう傾向のある人は、まとめ買いの予算決めから始めてみましょう。
スーパーで使う食費を月4万円にしたい人は週1万円、月3万円にしたい人は週7,500円が目安といった具合です。その中で、肉・魚コーナーではいくらぐらい、野菜コーナーではいくらぐらい、そのほかでいくらぐらいなど、スーパーで食材を選ぶときの量のバランスに慣れていきましょう。
また、少しずつでいいので、作り置きや冷凍保存を取り入れて食材使い切りや時短料理に役立てていけるといいですね。
4.ワーママの収入はすべて貯金
共働き家庭の最強パターンといってもいいのが、「ワーママの収入をすべて貯金に回す」家計やりくり。夫の収入がある程度必要となる方法ですが、「私も働いているのだから、これぐらいの贅沢はいいよね」というちょこちょこした出費を生み出す考えを排除しやすくなります。
いきなり「ワーママの収入はすべて貯金」となるとハードルが高いと感じられる場合は、「月○万円」などの先取り貯蓄から始めてもよいでしょう。貯金に対する夫の意識も高めるために、夫婦それぞれで「夫は○万円」「妻は○万円」と先取り貯蓄額を決める方法もおすすめです。
(※本ページに記載されている情報は2020年3月3日時点のものです)